 疲れるママ
疲れるママ子どもの「これ買って!」。
ダメって言えば泣くし、いいよって言えばキリがない…
どうしたらいいの〜?



そんなときこそ金融教育のチャンスだよ!
わが家には、5歳と2歳の子どもがいます。
とくに5歳の長男は、買い物に行くたびに「あれが欲しい!」「これも欲しい!」の連発。
最初は、どうしたらいいのか本当に悩みました。
でもふと思ったんです。



これって、お金のことを教えるチャンスかも!
そこから、わが家なりの「おもちゃの買い方ルール」を考えはじめました。
小さな工夫ですが、少しずつ子どもの変化も見えてきて…。
この記事では、わが家で実践している「おもちゃの買い方」を通じた、わが家流金融教育についてご紹介します!
おもちゃを買うときの3つのポイント
子どもに「欲しい!」と言われたとき、わが家ではこの3つを大切にしています。
- おもちゃを買うのは「予算の範囲内」と伝える
- おもちゃを買うタイミングを事前に決めておく
- 時間が経っても欲しいと思うものなら買う



ひとつずつ解説していくね!
1.おもちゃを買うのは予算の範囲内で!と伝える


買い物中、特に予定はなかったのに子どもに「あれ、買って」と言われたらどうしますか?
わが家では、そんなときたいてい次のように返していました。
・【たしなめる】「今日は、おもちゃを買いに来たんじゃないんだよ」
・【思い出させる】「それと似たおもちゃ、家になかったっけ?」
・【気をそらす】「あ、こっちにおもしろそうなのあるよ!」
・【断る】「お金がないから無理だよ」
特に「金がないから無理だよ」と、少し違和感を感じつつも、よく口にしてしまっていました。
その違和感の理由を考えてみると、この言葉には次のようなマイナスの印象を与える可能性があることに気づいたんです。
- 親に「お金がない」と言われると、子どもは不安になるかもしれない
- 「お金があったら、たくさん使っていい」と、子どもが思うかもしれない
親として本当に伝えたいのは、次の2つのことでした。
- お金はあるけれど、使っていい金額には限りがあるということ
- 使いすぎると生活に影響が出るから、計画的に使う必要があるということ
このメッセージをどう伝えればいいか悩んでいたときに、ふとピッタリの言葉に出会いました。
「予算の範囲で買い物する」という考え方は、大人になってもとても大切なこと。
それに気づいてからは、こんなふうに言い換えるようになりました。
「今買っちゃうと予算がなくなって、本当に欲しいものが買えなくなるよ。お誕生日かクリスマスに欲しいものを買おうね」
「予算」という言葉は小さい子どもにとっては少し難しい言葉かもしれませんが、5歳の息子はなんとなく受け入れてくれています。
もし、分かっていなかったとしても、親が何度も伝え続けることで、いつかその重要性に気づいてくれたら…なんて思っています。
2.おもちゃを買うのは誕生日とクリスマスだけと伝える
わが家では「おもちゃを買ってもらえるのは、誕生日と、クリスマスだけ」と子どもに伝えています。
お店でとても欲しそうにしている姿を見ると、つい買ってあげたくなるのが親心。
でも、ここは親もグッと我慢…。
このルールだけは守るようにしています。
「おもちゃを買うタイミング」をあらかじめ決めておくと、実はとても良いことがあるんです。
わが家が感じているメリットは次の3つ
- 必要以上におもちゃが増えすぎない
- 今あるおもちゃを大事に使うようになる
- 誕生日やクリスマスが、より楽しみなイベントになる
このルールを続けているおかげか、長男も「そういうものなんだ」と自然に受け止めてくれるようになりました。
もちろん、ほしいおもちゃをすぐに買ってもらえないのは残念そうにすることもありますが、だんだんと我慢できるように。
最近では、「これにしようかな?」「やっぱりこっちもいいな〜」と、誕生日やクリスマスに何をお願いするか、ワクワクしながらじっくり考えるのが楽しみになっているようです。



「これが欲しいな、あれが欲しいな」と、まるで旅行に行く計画を立てているときのように、楽しそうに考えているよ!


3.時間をかけても欲しいと思うものであれば買う
ここまでで2つのポイントをお伝えしましたが、実際に買い物へ行くと、目の前に気になるおもちゃがあると、やっぱり「欲しい!」という気持ちが強くなりますよね。
それは子どもに限らず、大人だって同じです。
特に小さな子どもは、「今、これが欲しい!」という気持ちがとても強くて、ついダダをこねてしまうこともあります。
わが家でも、長男が3歳の頃はよくありました。
お店でおもちゃを見つけると、「買ってー!」とその場を動かなくなってしまうこともしばしば…。


そんなときに活躍したのが、「覚えておこう作戦」です。
これはとても簡単で、100円ショップなどで見つけた「ちょっとしたおもちゃ」や、「プレゼントにはちょっと…」というような物にも使えるおすすめの方法です。
やり方はこうです。
「このおもちゃ、気になるんだね。じゃあ覚えておこうか。
2週間〜1か月くらい経っても、まだ欲しいなって思ってたら、本当に欲しいものかもしれないから、その時また考えようね。」
こんなふうに伝えるだけ。
お店が写真撮影OKであれば、実際に商品をパチリと撮って「ママも覚えておくね」と伝えると、さらに効果的です。
この方法、わが家では思った以上にうまくいきました。
子どもも納得しておもちゃを棚に戻し、スムーズにお店を出られるようになったんです。
「覚えておくね」と伝えるだけで、子どもは「自分の気持ちをちゃんと受け止めてもらえた」と感じるのかもしれません。



親の共感が伝わると、子どもも安心するんだよね。
実際に、その場の勢いで欲しくなったおもちゃは、数日たつと忘れてしまっていることがほとんどでした。
たぶん、そういうものを買っていたとしても、あまり遊ばなかったと思います。
逆に、時間が経っても「やっぱり欲しい!」と言い続けたものは、後日プレゼントとして買ってあげるようにしています。
そういったものは、本当に欲しかっただけあって、もらったときの喜びもひとしお。
大事に扱って、長く遊んでくれています。
買う・買わないの体験が、学びになる
わが家では、まだお小遣い制を導入していないため、子どもが欲しいものは基本的にすべて親が買っています。
その分、おもちゃの選び方や買うタイミングには、どうしても親の意見が大きく影響しているかもしれません。
でも、これから子どもがもう少し大きくなって、自分でお金を管理できるようになったら少しずつ「何を買うか」の決定を本人に任せていく必要があると感じています。
とはいえ、
- 予算の範囲で買う
- 計画的に買い物をする
- 衝動買いせず、必要かどうかじっくり考える
こうしたことは、何歳になっても大切な力。
だからこそ、今のうちから少しずつ、買い物のルールや考え方を伝えていけたらと思っています。
まずは、おもちゃを買う頻度を「誕生日とクリスマスだけ」と決めるところから始めてみませんか?



わが家で効果のあった『覚えておこう作戦』も、ぜひ一度試してみてね!




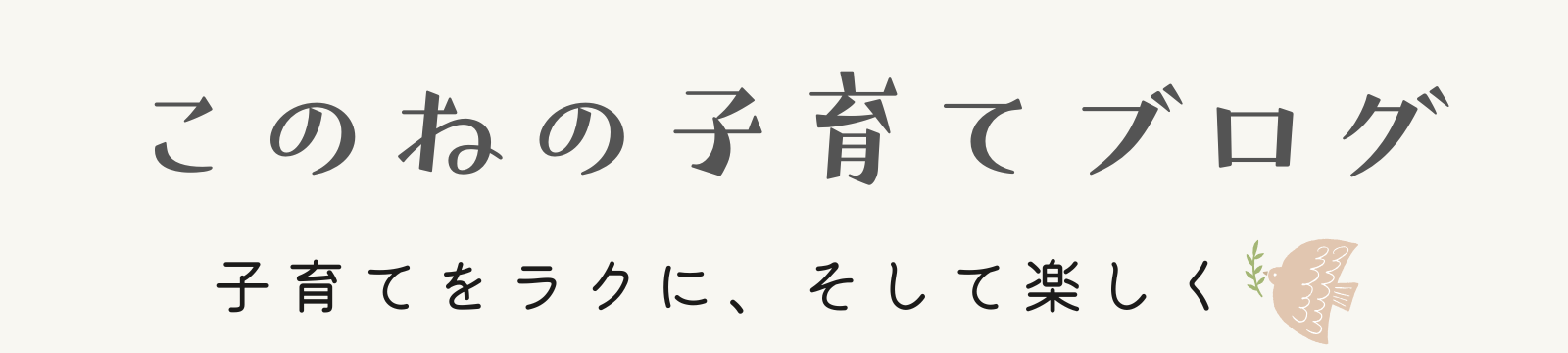
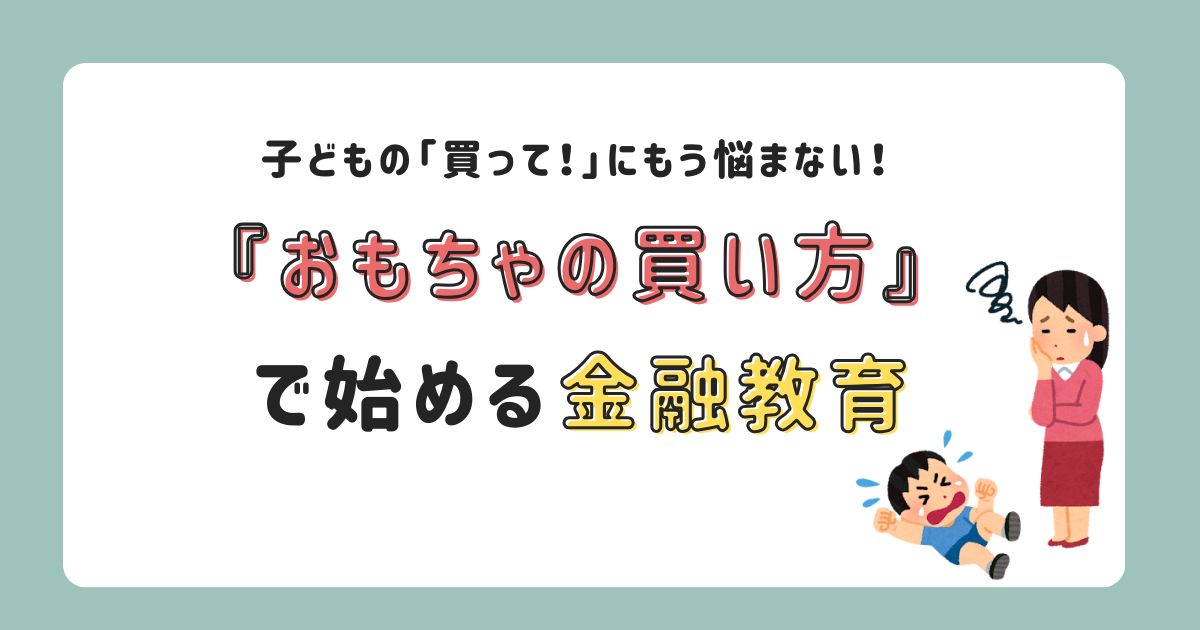
コメント